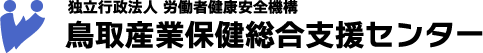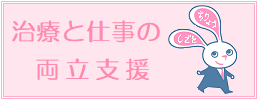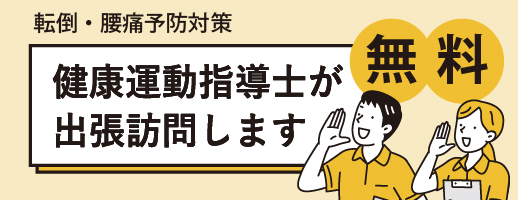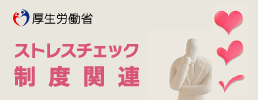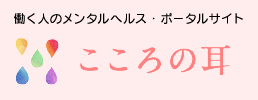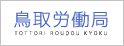鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
産業保健(労働衛生)は、あらゆる職業に従事する人々の業務に起因する負傷・疾病・障害・死亡などの健康障害の発生を未然に防止することと、労働者の健康増進や快適な作業環境の構築することを目的としている。このことにより企業の生産性の向上がはかられ、業務の人間への適合と人間の業務への適応がはかられることが期待されている。
また、労働者の精神的・肉体的・社会的健康の増進からはじまり、作業環境管理、作業管理、健康管理のいわゆる労働衛生の三管理を総合的に実践することにより、今日的課題である過重労働の防止、メンタルヘルス対策など、心の安全・安心・人間関係の良好な体制づくりにまで対応するようになっている。
医学分野の労働衛生では、主にいわゆる職業病の原因と病態の解明を行うことによって疾病の予防体制を確立することを行っていましたが、いわゆる職業病などに関係した特殊健診よりも、生活習慣病に関する健康診断が多く実施されている。
また、山陰労災病院では、病院の開設当初から長い間、女性の労働を軽視していたこともあって、診療科に産婦人科を設置していなかったが、2013年に産婦人科が開設され、それに伴い小児科も開設され、総合病院として機能するようになった。
産業保健の範囲も、メンタルヘルス(心の健康)、パワーハラスメント(パワハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)の予防にまで拡大されているので、産業保健従事者は今までの活動の範囲を越えて活動したり対応する必要がある。
産業医や産業看護職そして衛生管理者などのあり方も労働と疾病という関係のみではなく、職業に従事する人間として労働者に対応し、生活全体(職場、家庭、社会生活)を考慮に入れた健康管理と指導が大切となっている。
その上、人口の高齢化に伴い労働者年齢が上昇したことにより、年齢に応じた労働者の身体機能を十分に考慮した作業の工夫と適性配置を実践しなくてはならなくなった。これらのことなど、急速に変化する労働者の状況に対応した支援を可能にする体制を実現しなくてはなりません。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
産業保健を支援する実施体制は、47の都道府県に、その拠点として「産業保健総合支援センター」(以下センターという、鳥取県では、鳥取市扇町に設置)と地域産業保健事業を支援する地域の窓口(地域産業保健センター、鳥取県では、東・中・西部の医師会館内に設置)が連携して行っています。
センターは県内全事業場を対象として専門的な産業保健(メンタルヘルスを含む)相談、産業保健スタッフの研修、産業保健に関わる情報提供等を実施し、地域の窓口(地域産業保健センター)は県内の主に労働者50人未満の小規模事業場を対象として、労働者の健康増進(メンタルヘルスを含む)に関する相談、健康診断の結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者に対する面接相談など広く実施しています。また、メンタルヘルス対策支援事業とも一元化され、こころとからだの相談が一度の手続きで「ワンストップサービス」として必要な支援が受けられるようになりました。
産業保健サービスも時の流れにつれて内容が変化して、作業環境管理や作業管理が改善されたことにより、特に職業性疾病は業務上の負傷や事故を除けば、物理・化学的因子や中毒による疾病は激減しています。それに変わり、定期健康診断では、生活習慣病のような一般疾病が労働者の健康に影響を与えています。また、作業内容の変化や職場の人間関係が複雑化することによりストレスなどによる精神障害に関する事象も増加し、産業保健対策も更に進化し検討しなくてはならないと思っています。
生活習慣病管理は医療との連携が重要であり、産業保健を担当するスタッフ(医師・保健師・衛生管理者等)は、臨床医学的知識・技能・対応を習得する必要があり、産業保健スタッフ研修のテーマにも生活習慣病などについて取り入れると共に、センターや地域の窓口は医師会機能に密着して運営することも視野に入れる必要を感じています。これらのことを念頭に入れ、産業保健の支援事業もさらに発展させるため活動の方向を充実改善することが大切と考えています。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
大型連休も明けて、”休みぼけ”から仕事に体調を合わせることに努めている人も多いと思います。
季節の移り変わりも早く、この間まで桜見物を話題にとりあげていましたのに、もう つつじも満開となり、松の木の「みどり摘み(今年新しく伸びはじめた新芽を摘み風雅な樹形を調えるために美しい枝振りをつくる手入れをすること)」をしなくてはならない時期になりました。
新入社員も会社組織や仕事内容に上手に適合する者もいれば、「五月病」にかかり、職場に適合出来ず一人で悩んでいる者もでてくる時期であると推測されます。
そのため、「みどり摘み」のように手入れ(適切な相談と指導、助言)をしてやることによって、それぞれの職場に適合出来るような体制を調える時期でもあります。
仕事に上手に適合した者はほめてやり、一層その人の特徴を伸ばすことの出来る体制をつくることや適合困難な者には、メンタルヘルスの不調を未然に防止するため、一次予防(精神的健康の保持・増進)の実践が必要な場合があるでしょう。
携帯電話のメールでコミュニケーションに慣れた世代を育てるための方策に”赤ちょうちんで飲んで話し合う”では、とても共感や理解をえることができるとは思えません。
人事課の担当者や上司など管理者は産業医等と相談して、ストレスチェックを活用して各個人のストレスの程度や内容を把握し、個別の課題に対応する策を講じることが重要となります。
産業保健総合支援センターでは、専門的相談員の指導を受けながら、地域産業保健センターでは鳥取県内の東・中・西の各医師会に配属されているコーディネーターを通じて、それぞれの事業場の協力を得ながら、取組みやすい体制を調えていく予定です。
産業保健の発展のために、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
新年度になり、日本では入学式や入社式などを迎え、各部署では、新人や新任の者が活動をはじめ、人事異動の者も新しい職場で今まで以上の実力を発揮するように気持ちを新たに行動を開始しています。
自己紹介がおそくなりましたが、本年4月1日より本センターの所長に就任いたしました能勢です。よろしくお願い申し上げます。産業保健の分野を大学の教官に就任して以来、教育・研究の重要な課題として取り組んでまいりました。
産業保健の課題は急速に時代の流れとともに変遷しています。私が産業保健に携わるようになった頃は劣悪な作業環境が多くあったため、いわゆる職業病(鉛中毒、振動障害、じん肺、有機溶剤中毒、各種化学物質の中毒疑いなど)がかなりあり、労働者健康診断も特異な分野の医学の実践をすることが多くありました。それが今日では生活習慣病やメンタルヘルスなどポピュラーな疾患を視野に入れた健康診断がややもすると主流となった労働者の健康管理になっています。
古い桜の木が毎年美しい花を咲かせていて、昔の人もこの木を花を見て楽しんだのであろうと懐古にひたっていると、すぐ横で若い木が植樹され若い芽を出し古い木が朽ちても次世代が育っています。
この若い木が隆盛してくれるのも、そんなに遠くはないと感じています。
経験豊富な先達は未経験の世代がしっかり育つまで道を示すと同時に体制をつくっておくことが大切です。
不景気になると、労働環境が劣化しかねません。快適な労働環境を維持し続けるのがなんとなく困難になっていくことを感じます。
4月という新旧交代の時期、改めて社会に大切なことは何かを見据えて諸現象に対応することが必要と思います。
本センターは、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業、及び地域産業保健事業の3事業を一元化して、平成26年4月1日にスタートしています。
産業保健関係者を支援するとともに、職場の健康管理への啓発の目的を達成するため、みなさまの御理解と御支援を得る事によって本センターの機能が発揮出来るように努力しますと共に尽力したいと思っています。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 川﨑 寛中
全国的にインフルエンザの流行はピークを過ぎましたが、引き続きインフルエンザ対策を怠らないようにしてください。インフルエンザが下火になり、終息する頃から花粉症の時期に入ります。日本では直近10年間でスギ・ヒノキ花粉量が大幅に増加しており、特に前年7月~8月の平均最高温度が高いほど飛散量が多いと言われます。昨年7月の猛暑から推測すると、今年は花粉症が多発する可能性がありますので、毎年花粉症に悩まされる人は早めの対応で症状軽減と仕事の上での思考力や集中力維持に努めてください。
3月は自殺対策強化月間です。近年、全国的に自殺者数は減少傾向にありますが、一方では働き盛りの20、30、40歳代の死因で自殺者数が多いことが課題になっています。鳥取県の自殺者(自死)数はやや低下傾向にありますが、自死率は全国より高い値で推移している現状です。
昨年の労働安全衛生法改正で、労働者の心理的な負担の程度を把握するための医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施が今年の12月1日から事業場に義務付けられます。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務となっています。(公財)日本生産性本部・メンタル・ヘルス研究所は昨年、「メンタルヘルスの取り組み」に関する上場企業250社の調査を取りまとめた結果、最近3年間の「心の病」の増減では、「増加傾向」と回答した企業は29.2%、「横ばい」は58.0%、「減少傾向」は9.2%で、「心の病」は依然として高止まり傾向にあります。「心の病」を年代別にみると、30代、40代が3割を上回っているのが大きな課題になっています。
当総合支援センターの黒沢洋一相談員の平成25年度産業保健調査研究報告書による「鳥取県のメンタルヘルスの取り組み状況~平成19年度調査との比較~」においても、過去一年間でメンタルヘルスに関連して不調を訴える事例があった事業場は全体の46%に上りますので、産業保健従事者は引き続き多角的なメンタルヘルス対策を講じてください。
3月の声を聞くと、桃の節句(3日)、啓蟄(6日)、彼岸入り(18日)、春分(21日)と続き、下旬にはいよいよ桜の開花を待つ時期となります。事業場では今月は平成26年度最後の月になりますので、年度内の目標を確実に達成して新しい年度に移りたいものです。